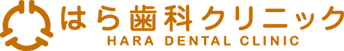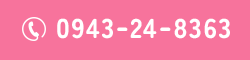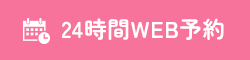お役立ちコラム
親知らずの抜歯
 歯科医院を受診するきっかけとして親知らずの抜歯を目的として受診される方は多くいらっしゃいます。
歯科医院を受診するきっかけとして親知らずの抜歯を目的として受診される方は多くいらっしゃいます。
特に現代人は、縄文人などと比べて顎の骨が小さく、歯が並ぶスペースが不足していることから、親知らずがうまく生えずに横を向いて生えてきたり、そもそも親知らず自体がなくなっていたりすることもあります。
親知らずは、歯の並びの一番奥に生える歯であり、本来であれば歯として機能すべきものではありますが、うまく生えないことで歯周病やむし歯などのリスクになっていたり、歯並びに悪影響を及ぼしている場合などでは抜歯の適応となります。
特に一度でも、親知らずの周りが腫れたり、痛みが出たりした場合には、再度同様の症状を繰り返すことがあり、抜歯して原因を除去することが望ましいです。
今回は、親知らずの抜歯の適応や、抜歯に伴う注意点について説明していきます。
親知らずの抜歯の適応
・真っ直ぐに生えていない
・咀嚼などの機能を果たしていない
・むし歯や歯周病の原因になっている
・親知らずによって手前の歯に痛みや歯の吸収が生じている
このような場合には、親知らずは抜歯の適応であるといえます。
抜歯に伴う注意点
親知らずの抜歯は、少なからず体に影響を与える、外科的侵襲のある処置です。
そのため、事前に注意点を理解しておき、親知らずを残しておくよりも、抜歯によるメリットが上回った時に抜歯を行う必要性があると判断します。
抜歯に伴う主な注意点は、抜歯を行う歯が上の親知らずか、下の親知らずかによって異なります。それぞれについて説明していきます。
上の親知らずの抜歯に関する注意点
上の親知らずは、鼻の空洞である上顎洞と位置が近いことがあり、抜歯によって口腔内と鼻腔とが交通してしまうことがまれにあります。もし万が一、交通してしまった場合には、生じた穴の大きさによって自然治癒を待ったり、糸で縫合したりします。穴が開いた箇所から感染が生じた場合には、上顎洞炎といい、上顎洞内に膿がたまる、蓄膿症のような症状が生じます。その場合には、抗菌薬を投与するなどして対応します。
下の親知らずの抜歯に関する注意点
下の親知らずは、下顎管といい、下唇から顎先の触られた感覚を司る神経や、大きな血管が入っている管に近接していることがあり、万が一損傷が生じると、触れた時の感覚が鈍くなったり、痺れたような症状が生じたりします。また、血管損傷が生じた場合には、出血が多少に生じることがあります。神経の症状に関しては、自然治癒を認めることが多いですが、明らかな感覚障害が生じている場合には、神経の修復を促すビタミン剤の内服を行ったり、レーザー治療によって神経の改善を促したりします。
血管の損傷が起こった場合には、圧迫止血や止血剤を用いた止血処置などを行います。
上下の親知らずに共通する注意点
 抜歯後には、抜歯後感染といい、抜歯した部位が口腔内の細菌によって感染を生じることがあります。抜歯後感染を予防する目的で、一般に抗菌薬が処方されますが、用法用量を守って内服をするだけでなく、口腔清掃をきちんと行い、処置の前後で口の中の細菌の数を減らしておくことも大切です。
抜歯後には、抜歯後感染といい、抜歯した部位が口腔内の細菌によって感染を生じることがあります。抜歯後感染を予防する目的で、一般に抗菌薬が処方されますが、用法用量を守って内服をするだけでなく、口腔清掃をきちんと行い、処置の前後で口の中の細菌の数を減らしておくことも大切です。
また、外科的な侵襲が加わる処置であるため、術後数日間は、痛みや腫れが生じたり、微量の出血が続いたりすることもありますが、痛みや腫れについては痛み止め(抗炎症薬)を内服することで対応します。これらの症状は、自然治癒することがほとんどのため、必要以上に心配することはせず、基本的には経過を見ていきます。
特に、下の親知らずの抜歯で、骨を削る場合や下顎管と親知らずの近接を認めた場合などでは、腫れや痛みの症状が強く出ることもあります。術後2〜3日がピークであることが多く、その後は自然消退していきます。
以上が、親知らずの抜歯の適応と、抜歯に関する主な注意事項です。
その他に心配なことがあれば、歯科医院で尋ねてみてください。
はら歯科クリニック
 当院では、小さなお子さまからご家族連れ、ご高齢の方までが安心して通院して頂けるように、キッズルームやお子さま専用の治療室、バリアフリーを整え、様々な年齢層の患者さんが通いやすい医院づくりを徹底しております。
当院では、小さなお子さまからご家族連れ、ご高齢の方までが安心して通院して頂けるように、キッズルームやお子さま専用の治療室、バリアフリーを整え、様々な年齢層の患者さんが通いやすい医院づくりを徹底しております。
「歯医者さんは怖い」というイメージを払拭できるよう、雰囲気やBGMにもこだわり、ゆったりと過ごしていただける医院づくりに努めています。
歯のメンテナンスや治療をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
住所:〒834-0104 福岡県八女郡広川町大字吉常357-1
TEL:0943-24-8363